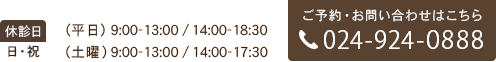歯ぎしりがあってもインプラントは可能?諦める前の全知識|リスクと対策を専門医が徹底解説
医院ブログ
「歯ぎしりの癖があるから、インプラントは無理かもしれない」
「高額な治療なのに、歯ぎしりでダメになったらどうしよう」
歯ぎしりや食いしばりはインプラントにとって大きな負担となる可能性があります。
しかし、適切な診断と対策を行えば、歯ぎしりの癖がある方でもインプラント治療を成功させることは十分に可能です。
この記事では、歯ぎしりがインプラントに及ぼす具体的なリスクから、そのリスクを乗り越えるための専門的な対策、そして歯科医院選びのポイントまでを詳しく解説します。
大切な歯のために後悔のない選択ができるよう、ぜひ最後までお読みください。
なぜ歯ぎしりはインプラントに良くないのか?

歯ぎしりがインプラントにとって大きなリスクとなるのはインプラントとご自身の天然の歯との間にある、構造上の決定的な違いに起因します。
その違いを理解することが、適切な対策を講じる第一歩となるのです。
天然歯との決定的な違い「クッション機能」がないインプラント
私たちの天然の歯は、歯根と顎の骨の間に「歯根膜(しこんまく)」という薄い膜が存在します。
この歯根膜は、食事や食いしばりの際に歯にかかる強い力を吸収し、分散させるクッションのような重要な役割を果たしています。
一方で、インプラントは顎の骨と直接結合しているため、この歯根膜が存在しません。
そのため、歯ぎしりのような過剰な力がかかった場合、その衝撃が直接インプラント本体と周囲の骨に伝わってしまうのです。
睡眠中は体重の2倍以上!インプラントに直接かかる過剰な力
睡眠中の無意識下で行われる歯ぎしりは、日中の噛む力とは比べ物にならないほどの負荷を生み出します。
研究によれば、歯ぎしりをしている方の噛む力は1000N(ニュートン)を超えることもあり、これはご自身の体重の2倍以上の力に相当します 。
クッション機能を持たないインプラントが、これほど強大な力を繰り返し受け続ければ、様々なトラブルを引き起こす原因となりかねません。
歯ぎしりが引き起こすインプラントの5大トラブル
では、歯ぎしりによる過剰な力がインプラントにかかり続けると、具体的にどのような問題が起こるのでしょうか。
ここでは、特に注意すべき代表的な5つのトラブルを紹介します。
トラブル1 人工歯(被せ物)の破損・脱落
最も起こりやすいトラブルの一つが、インプラントの上に取り付けられた人工歯(上部構造)の破損です。
いくら丈夫なセラミックなどの素材で作られていても、毎晩のように強い力がかかれば、欠けたり割れたりするリスクが高まります。
また、人工歯を固定しているネジが緩み、外れてしまうこともあります。
トラブル2 インプラント本体の緩み・脱落
さらに深刻なのは、顎の骨に埋め込まれたインプラント本体(フィクスチャー)に影響が及ぶケースです。
継続的な強い力は、インプラントと骨との結合を破壊し、インプラントの緩みを引き起こすことがあります。
この状態を放置すると、最終的にはインプラントが抜け落ちてしまい、再治療が必要になる可能性が出てきます。
トラブル3 インプラント周囲炎のリスク増大
歯ぎしりは、インプラントの天敵である「インプラント周囲炎」のリスクも高めます。
過剰な力がインプラントにかかることで、インプラントと歯茎の間に微細な隙間が生まれ、そこに細菌が侵入しやすくなるのです。
インプラント周囲炎は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行し、インプラントを支える骨を溶かしてしまう恐ろしい病気です。
トラブル4 土台となる顎の骨が溶ける(骨吸収)
歯ぎしりのような過剰な負担が長期間にわたってかかり続けると、骨は耐えきれずに吸収され、溶けてしまうことがあります。
土台である骨が失われれば、インプラントはその安定性を失い、ぐらつきや脱落の原因となります。
トラブル5 顎の痛みや頭痛(顎関節症)
顎の関節やその周りの筋肉にも過剰な負担がかかるため、顎関節症を引き起こすことがあります。
「口を開けるとカクカク音がする」「顎が痛くて口を大きく開けられない」といった症状のほか、関連して頭痛や肩こりを訴える方も少なくありません。
歯ぎしりがあってもインプラント治療ができるか判断する基準

ここまで読んで、「自分も歯ぎしりをしているかもしれない」と不安になった方もいるでしょう。
ここでは、ご自身でできる簡単なセルフチェックと、歯科医院で行う専門的な診断方法について解説します。
まずはセルフチェック!歯ぎしりをしているサイン
睡眠中の歯ぎしりは無意識に行われるため、自覚していないケースがほとんどです。
以下の項目に心当たりがないか、一度チェックしてみましょう。
治療の可否を決める専門的な診断とは?(咬合力測定・CT検査など)
セルフチェックで当てはまる項目があった場合でも、すぐにインプラントができないと決まるわけではありません。
大切なのは、歯ぎしりの種類や強さ、頻度を客観的に評価し、リスクを正確に把握することです。
そのため、専門の歯科医院では以下のような精密な検査を行います。
これらの検査結果を総合的に分析することで、歯ぎしりのリスクを管理しながら、安全にインプラント治療を進められるかどうかを判断します。
歯ぎしりから大切なインプラントを守るための4つの対策

現在では、インプラントを過剰な力から守るための効果的な対策が確立されています。
ここでは、代表的な4つの方法をご紹介します。
対策1 マウスピース(ナイトガード)で力を緩和
歯ぎしり対策として、最も基本的かつ効果的なのが、就寝中に装着するオーダーメイドのマウスピース(ナイトガード)です。
これは、歯ぎしりそのものを止めるものではありませんが、歯やインプラントにかかる力を吸収・分散させ、ダメージを大幅に軽減する役割を果たします。
対策2 噛み合わせの精密な調整
特定の歯やインプラントにだけ強い力が集中しないよう、咬合力を均等に分散させることで、歯ぎしりによるダメージのリスクを軽減できるのです。
専用の機器を用いて噛む力のバランスを細かく分析し、ミリ単位での調整を行います。
対策3 重度の方向けのボトックス注射という選択肢
ナイトガードを使用しても、歯ぎしりによる症状が改善されない重度の方には、ボトックス注射という治療法も選択肢の一つです。
これは、噛むための筋肉(咬筋)にボツリヌストキシン製剤を注射することで、筋肉の緊張を和らげ、歯ぎしりの力を根本的に弱める治療法です。
対策4 ストレス管理など生活習慣の見直し
歯ぎしりの大きな原因の一つに、精神的なストレスが挙げられます。
そのため、歯科的なアプローチと並行して、ご自身の生活習慣を見直すことも大切です。
歯ぎしりに強いインプラント治療とは?宝沢伊藤歯科医院の取り組み
ここからは、福島県郡山市の宝沢伊藤歯科医院が、歯ぎしりのリスクを抱える患者様に対して、どのように向き合い、安全で確実な治療を提供しているかをご紹介します。
20年・1,500本以上の実績と日本補綴歯科学会専門医による安心の執刀
当院の院長は、20年以上にわたりインプラント治療に携わり、これまでに1,500本以上の埋入実績を積み重ねてまいりました(2024年度の成功率98.5%)。
さらに、噛み合わせや被せ物の専門家である「日本補綴歯科学会専門医」の資格を有しており、すべてのインプラント治療を院長自らが担当します。
豊富な経験と専門知識に基づき、歯ぎしりのリスクを正確に見極め、一人ひとりに最適な治療計画をご提案します。
CT・シミュレーションソフト(SimPlant)で実現する「力の分散」を考慮した精密治療
安全なインプラント治療の基礎となるのが、正確な術前診断です。
当院では、歯科用CTによる3D画像診断に加え、SimPlantというコンピュータ解析ソフトウェアを活用しています。
これにより、骨の量や質、神経の位置を精密に把握するだけでなく、歯ぎしりによる力がインプラントにどのようにかかるかをシミュレーションし、負荷を最大限に分散できる最適な位置・角度・深さにインプラントを埋入する計画を立案します。
他院で断られた難症例にも対応する骨造成(GBR・サイナスリフト)
当院では、年間平均でサイナスリフト15件、GBR(骨造成)10件という豊富な実績があり、骨の量が不足している難症例にも対応可能です。
失われた骨を再生させる高度な技術によって、インプラント治療を諦めていた方にも、再び噛める喜びを取り戻すお手伝いをします。
治療後も安心の「ガイドデント10年保証」と専門的なメンテナンス体制
高額なインプラント治療だからこそ、治療後の保証は患者様にとって大きな安心材料となります。
当院では、第三者機関である「ガイドデント」によるインプラント10年保証制度を導入しており、万が一のトラブルにも迅速に対応できる体制を整えています。
また、インプラントを長持ちさせるためには、治療後の定期的なメンテナンスが欠かせません。
【まとめ】歯ぎしりを理由にインプラントを諦めないでください
歯ぎしりは、インプラント治療における無視できないリスク因子です。
重要なのは、以下の3つのポイントです。
もしあなたが歯ぎしりを理由にインプラント治療を迷っているのであれば、まずは一度、専門家にご相談ください。
宝沢伊藤歯科医院では、患者様のお悩みや不安に寄り添う「クリニカルコーディネーター」が、まずはお話をじっくりお伺いします。
あなたの口腔内の状態を正確に診断し、リスクと可能性の両方を丁寧にご説明した上で、最適な治療法を一緒に考えていきましょう。
「高額な治療なのに、歯ぎしりでダメになったらどうしよう」
歯ぎしりや食いしばりはインプラントにとって大きな負担となる可能性があります。
しかし、適切な診断と対策を行えば、歯ぎしりの癖がある方でもインプラント治療を成功させることは十分に可能です。
この記事では、歯ぎしりがインプラントに及ぼす具体的なリスクから、そのリスクを乗り越えるための専門的な対策、そして歯科医院選びのポイントまでを詳しく解説します。
大切な歯のために後悔のない選択ができるよう、ぜひ最後までお読みください。
なぜ歯ぎしりはインプラントに良くないのか?

歯ぎしりがインプラントにとって大きなリスクとなるのはインプラントとご自身の天然の歯との間にある、構造上の決定的な違いに起因します。
その違いを理解することが、適切な対策を講じる第一歩となるのです。
天然歯との決定的な違い「クッション機能」がないインプラント
私たちの天然の歯は、歯根と顎の骨の間に「歯根膜(しこんまく)」という薄い膜が存在します。
この歯根膜は、食事や食いしばりの際に歯にかかる強い力を吸収し、分散させるクッションのような重要な役割を果たしています。
一方で、インプラントは顎の骨と直接結合しているため、この歯根膜が存在しません。
そのため、歯ぎしりのような過剰な力がかかった場合、その衝撃が直接インプラント本体と周囲の骨に伝わってしまうのです。
| 比較項目 | 天然歯 | インプラント |
|---|---|---|
| 構造 | 歯根と骨の間に歯根膜がある | 骨と直接結合している |
| クッション機能 | あり(歯根膜が衝撃を吸収) | なし |
| 力のかかり方 | 衝撃が緩和されて伝わる | 衝撃がダイレクトに伝わる |
| 歯ぎしりへの耐性 | 比較的高い | 比較的低い |
睡眠中は体重の2倍以上!インプラントに直接かかる過剰な力
睡眠中の無意識下で行われる歯ぎしりは、日中の噛む力とは比べ物にならないほどの負荷を生み出します。
研究によれば、歯ぎしりをしている方の噛む力は1000N(ニュートン)を超えることもあり、これはご自身の体重の2倍以上の力に相当します 。
クッション機能を持たないインプラントが、これほど強大な力を繰り返し受け続ければ、様々なトラブルを引き起こす原因となりかねません。
歯ぎしりが引き起こすインプラントの5大トラブル
では、歯ぎしりによる過剰な力がインプラントにかかり続けると、具体的にどのような問題が起こるのでしょうか。
ここでは、特に注意すべき代表的な5つのトラブルを紹介します。
| トラブルの種類 | 概要 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 人工歯の破損・脱落 | インプラントの被せ物が欠けたり、割れたり、外れたりする。 | 見た目の問題、食事のしづらさ |
| インプラント本体の緩み・脱落 | 骨と結合したインプラント自体が揺れ始め、最悪の場合抜け落ちる。 | 見た目の問題、食事のしづらさ |
| インプラント周囲炎 | インプラント周辺の歯茎や骨が炎症を起こし、進行すると骨が溶ける。 | 歯茎の腫れ、出血、膿 |
| 顎の骨の吸収 | 過度な負担により、インプラントを支える顎の骨が溶けてしまう。 | インプラントの安定性の低下 |
| 顎関節症 | 顎の関節や筋肉に負担がかかり、痛みや口の開けにくさを生じる。 | 顎の痛み、口が開かない、頭痛 |
トラブル1 人工歯(被せ物)の破損・脱落
最も起こりやすいトラブルの一つが、インプラントの上に取り付けられた人工歯(上部構造)の破損です。
いくら丈夫なセラミックなどの素材で作られていても、毎晩のように強い力がかかれば、欠けたり割れたりするリスクが高まります。
また、人工歯を固定しているネジが緩み、外れてしまうこともあります。
トラブル2 インプラント本体の緩み・脱落
さらに深刻なのは、顎の骨に埋め込まれたインプラント本体(フィクスチャー)に影響が及ぶケースです。
継続的な強い力は、インプラントと骨との結合を破壊し、インプラントの緩みを引き起こすことがあります。
この状態を放置すると、最終的にはインプラントが抜け落ちてしまい、再治療が必要になる可能性が出てきます。
トラブル3 インプラント周囲炎のリスク増大
歯ぎしりは、インプラントの天敵である「インプラント周囲炎」のリスクも高めます。
過剰な力がインプラントにかかることで、インプラントと歯茎の間に微細な隙間が生まれ、そこに細菌が侵入しやすくなるのです。
インプラント周囲炎は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行し、インプラントを支える骨を溶かしてしまう恐ろしい病気です。
トラブル4 土台となる顎の骨が溶ける(骨吸収)
歯ぎしりのような過剰な負担が長期間にわたってかかり続けると、骨は耐えきれずに吸収され、溶けてしまうことがあります。
土台である骨が失われれば、インプラントはその安定性を失い、ぐらつきや脱落の原因となります。
トラブル5 顎の痛みや頭痛(顎関節症)
顎の関節やその周りの筋肉にも過剰な負担がかかるため、顎関節症を引き起こすことがあります。
「口を開けるとカクカク音がする」「顎が痛くて口を大きく開けられない」といった症状のほか、関連して頭痛や肩こりを訴える方も少なくありません。
歯ぎしりがあってもインプラント治療ができるか判断する基準

ここまで読んで、「自分も歯ぎしりをしているかもしれない」と不安になった方もいるでしょう。
ここでは、ご自身でできる簡単なセルフチェックと、歯科医院で行う専門的な診断方法について解説します。
まずはセルフチェック!歯ぎしりをしているサイン
睡眠中の歯ぎしりは無意識に行われるため、自覚していないケースがほとんどです。
以下の項目に心当たりがないか、一度チェックしてみましょう。
- 朝起きたとき、顎の筋肉に疲れやこわばりを感じる
- 歯がすり減って平らになってきた、または欠けている
- 頬の内側や舌に、噛んだような跡(圧痕)がついている
- 知覚過敏で、冷たいものがしみるようになった
- 家族やパートナーから、寝ているときの歯ぎしりの音を指摘されたことがある
- 原因不明の頭痛や肩こりに悩んでいる
治療の可否を決める専門的な診断とは?(咬合力測定・CT検査など)
セルフチェックで当てはまる項目があった場合でも、すぐにインプラントができないと決まるわけではありません。
大切なのは、歯ぎしりの種類や強さ、頻度を客観的に評価し、リスクを正確に把握することです。
そのため、専門の歯科医院では以下のような精密な検査を行います。
| 検査の種類 | 目的と内容 |
|---|---|
| 問診・視診・触診 | 自覚症状や生活習慣のヒアリング。歯の摩耗状態、筋肉の張りなどを確認。 |
| 歯科用CT検査 | 3D画像で顎の骨の量や質、神経の位置などを立体的に把握し、安全な手術計画を立案。 |
| 咬合力測定 | 専用の機器(T-Scanなど)で、噛む力の強さやバランス、力が集中している箇所を分析。 |
| 睡眠ポリグラフ検査(PSG) | (必要に応じて)睡眠中の脳波や筋活動を記録し、睡眠時ブラキシズムの重症度を診断。 |
これらの検査結果を総合的に分析することで、歯ぎしりのリスクを管理しながら、安全にインプラント治療を進められるかどうかを判断します。
歯ぎしりから大切なインプラントを守るための4つの対策

現在では、インプラントを過剰な力から守るための効果的な対策が確立されています。
ここでは、代表的な4つの方法をご紹介します。
対策1 マウスピース(ナイトガード)で力を緩和
歯ぎしり対策として、最も基本的かつ効果的なのが、就寝中に装着するオーダーメイドのマウスピース(ナイトガード)です。
これは、歯ぎしりそのものを止めるものではありませんが、歯やインプラントにかかる力を吸収・分散させ、ダメージを大幅に軽減する役割を果たします。
| 種類 | 素材・特徴 | こんな方におすすめ | 費用相場(保険適用外) |
|---|---|---|---|
| ハードタイプ | アクリルレジン製で硬い。耐久性が高く、力の分散効果に優れる。 | 噛む力が非常に強い方 | 30,000円~50,000円 |
| ソフトタイプ | アクリルレジン製で硬い。耐久性が高く、力の分散効果に優れる。 | 軽度の歯ぎしりの方、装着感を重視する方 | 15,000円~30,000円 |
| デュアルタイプ | 内側がソフト、外側がハード。装着感と耐久性を両立。 | 幅広い症例に対応可能 | 40,000円~50,000円 |
対策2 噛み合わせの精密な調整
特定の歯やインプラントにだけ強い力が集中しないよう、咬合力を均等に分散させることで、歯ぎしりによるダメージのリスクを軽減できるのです。
専用の機器を用いて噛む力のバランスを細かく分析し、ミリ単位での調整を行います。
対策3 重度の方向けのボトックス注射という選択肢
ナイトガードを使用しても、歯ぎしりによる症状が改善されない重度の方には、ボトックス注射という治療法も選択肢の一つです。
これは、噛むための筋肉(咬筋)にボツリヌストキシン製剤を注射することで、筋肉の緊張を和らげ、歯ぎしりの力を根本的に弱める治療法です。
対策4 ストレス管理など生活習慣の見直し
歯ぎしりの大きな原因の一つに、精神的なストレスが挙げられます。
そのため、歯科的なアプローチと並行して、ご自身の生活習慣を見直すことも大切です。
歯ぎしりに強いインプラント治療とは?宝沢伊藤歯科医院の取り組み
ここからは、福島県郡山市の宝沢伊藤歯科医院が、歯ぎしりのリスクを抱える患者様に対して、どのように向き合い、安全で確実な治療を提供しているかをご紹介します。
20年・1,500本以上の実績と日本補綴歯科学会専門医による安心の執刀
当院の院長は、20年以上にわたりインプラント治療に携わり、これまでに1,500本以上の埋入実績を積み重ねてまいりました(2024年度の成功率98.5%)。
さらに、噛み合わせや被せ物の専門家である「日本補綴歯科学会専門医」の資格を有しており、すべてのインプラント治療を院長自らが担当します。
豊富な経験と専門知識に基づき、歯ぎしりのリスクを正確に見極め、一人ひとりに最適な治療計画をご提案します。
CT・シミュレーションソフト(SimPlant)で実現する「力の分散」を考慮した精密治療
安全なインプラント治療の基礎となるのが、正確な術前診断です。
当院では、歯科用CTによる3D画像診断に加え、SimPlantというコンピュータ解析ソフトウェアを活用しています。
これにより、骨の量や質、神経の位置を精密に把握するだけでなく、歯ぎしりによる力がインプラントにどのようにかかるかをシミュレーションし、負荷を最大限に分散できる最適な位置・角度・深さにインプラントを埋入する計画を立案します。
他院で断られた難症例にも対応する骨造成(GBR・サイナスリフト)
当院では、年間平均でサイナスリフト15件、GBR(骨造成)10件という豊富な実績があり、骨の量が不足している難症例にも対応可能です。
失われた骨を再生させる高度な技術によって、インプラント治療を諦めていた方にも、再び噛める喜びを取り戻すお手伝いをします。
治療後も安心の「ガイドデント10年保証」と専門的なメンテナンス体制
高額なインプラント治療だからこそ、治療後の保証は患者様にとって大きな安心材料となります。
当院では、第三者機関である「ガイドデント」によるインプラント10年保証制度を導入しており、万が一のトラブルにも迅速に対応できる体制を整えています。
また、インプラントを長持ちさせるためには、治療後の定期的なメンテナンスが欠かせません。
【まとめ】歯ぎしりを理由にインプラントを諦めないでください
歯ぎしりは、インプラント治療における無視できないリスク因子です。
重要なのは、以下の3つのポイントです。
- ご自身の歯ぎしりの状態を精密検査で正確に把握すること
- マウスピースの装着や噛み合わせ調整など、適切な対策を継続すること
- 歯ぎしりへの深い知識と高度な技術を持つ、信頼できる歯科医院を選ぶこと
もしあなたが歯ぎしりを理由にインプラント治療を迷っているのであれば、まずは一度、専門家にご相談ください。
宝沢伊藤歯科医院では、患者様のお悩みや不安に寄り添う「クリニカルコーディネーター」が、まずはお話をじっくりお伺いします。
あなたの口腔内の状態を正確に診断し、リスクと可能性の両方を丁寧にご説明した上で、最適な治療法を一緒に考えていきましょう。